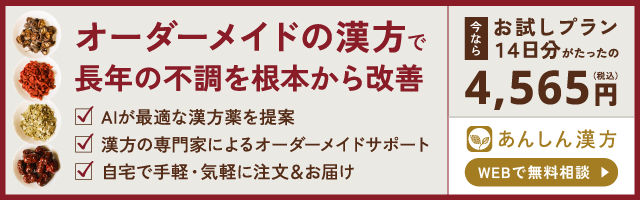東洋医学における「暑邪」と「津液」の概念
東洋医学では、自然界の気候変化が体調に影響を与えると考えます。特に夏には、「暑邪(しょじゃ)」と呼ばれる邪気が強まるとされます 。暑邪が体内に侵入すると高熱、口渇、多汗といった症状を引き起こします 。
暑邪の最大の特徴の一つは、体内の「気(エネルギー)」と「津液(しんえき)」を消耗させることです 。津液とは、血液以外のすべての体液の総称であり、涙、唾液、汗、尿、胃液などが含まれます 。津液は、皮膚や内臓、眼・鼻・口などの粘膜を潤し、関節の動きを滑らかにする働きを持っています 。暑邪によって大量の津液が消耗されると、体がだるくなったり、食欲不振になったり、重篤な場合には意識障害や気虚(エネルギー不足)を招くことがあります 。
日本の夏は高温多湿であるため、暑邪はしばしば「湿邪(しつじゃ)」と結びついて体内に侵入しやすいという特徴があります 。湿邪は重く粘る性質を持ち、体の中に停滞すると、津液の流れを滞らせてしまいます 。これにより、体が重だるく感じたり、むくみが生じたり、食欲不振や下痢といった胃腸の不調を引き起こすことがあります 。
東洋医学の観点から見ると、日本の夏の体調不良は、単なる「暑さ」だけでなく、この「暑邪」と「湿邪」が複合的に体に影響を及ぼすことで生じると考えられます。これは、体が重だるい、むくむ、胃腸の調子が悪いといった、西洋医学的な脱水症状だけでは説明しきれない夏の特有の不調を理解する上で非常に役立ちます。湿邪が津液の巡りを妨げることで、体内の水分バランスが乱れ、単に体を冷やすだけでは不十分で、体内の余分な湿気を取り除く対策も同時に重要になります。
夏の養生:食生活と生活習慣の知恵
東洋医学では、病気になる前の段階で健康を維持・増進する「養生」という考え方を重視します 。夏の養生は、暑邪と湿邪から体を守り、体内のバランスを整えることに主眼が置かれます。
- 食養生:
- 失われた「血」と「気」の補給: 薬膳では汗は「血」から作られると考えられており、大量に汗をかいた時には「血」を補う食べ物を摂ることが推奨されます 。また、暑邪によって消耗される「気(エネルギー)」を補う食材も重要です 。
- 体を冷まし、水分代謝を助ける食材: 体の熱を冷ます食材(ウリ科の野菜、苦味のある食材、赤色の食材)を積極的に取り入れましょう 。トマト、ナス、キュウリ、冬瓜、ゴーヤ、スイカ、ハトムギ、蕎麦など 。
- 甘味と塩味のバランス: 甘味のあるものは水分代謝を妨げるとされるため、塩辛いものと一緒に摂ることがポイントです 。
- 気(エネルギー)を補う食材: そら豆、かぼちゃ、うなぎ、鶏肉、高麗人参、山芋、牛乳など。
- 血を補う食材: 人参、ほうれん草、牛肉、レバー、ブドウなど 。
- 心を落ち着かせる食材: 小麦、鶏卵、うずらの卵、牛乳、なつめ、内臓のハツなど。
- 水分補給の工夫: 水分は一度に大量に摂取するのではなく、常温程度のものを少しずつこまめに摂るようにしましょう 。
- 消化に良い食事: 夏の暑い時期は胃腸の働きが弱まりやすいため、消化の良い食事を心がけることが重要です 。大根、シソ、ショウガなどの薬味は消化を助け、体内の湿気を取り除く効果が期待できます 。
- 生活習慣:
- 十分な休息: 体力消耗を防ぐため、十分な休息をとることが大切です 。昼寝もおすすめです
- 冷房との付き合い方: 冷房の効いた部屋で長時間過ごすと、体内の熱がうまく発散できずにこもってしまったり、体が冷えすぎて「冷房病」や「夏風邪」の原因になったりすることがあります 。設定温度を適切に保ち、体を冷やしすぎないよう注意しましょう 。
- 適度な発汗と入浴: 適度な運動や半身浴で汗をかくことは、体内の熱と湿気を排出するのに役立ちます 。湯船につかることは、温熱効果で自律神経を整え、水圧で全身の血流を促進し、浮力でリラックス効果をもたらします 。また、睡眠の質を改善し、毛穴を開いて老廃物を排出することで体臭防止にもつながるとされています 。ただし、過度な発汗は「気」や「陰(体内の水分や潤い)」を消耗し、だるさやボーっとする原因となるため、適度な範囲に留めることが重要です 。汗をかいたら早めにタオルで拭き、着替えることで「風邪(ふうじゃ)」の侵入を防ぎます 。
- 紫外線対策: 外出の際は、帽子や日傘、サングラスなどを活用し、暑さを軽減しつつ、紫外線から守ることも大切です.
熱中症対策に用いられる漢方薬
東洋医学では、熱中症や夏バテの症状に応じて、一例として下記のような漢方薬が利用されています。
- 漢方薬:
- 清暑益気湯(セイショエッキトウ): 汗による脱水と夏バテのだるさを一挙に立て直す処方とされます 。暑さで消耗する「気」や「陰」を補ってくれる良い漢方薬です 。
- 五苓散(ゴレイサン): 水分バランスを整える代表処方です。発汗、熱感、口渇、悪心、嘔吐、尿量減少、下痢のうちいくつか該当する場合に有効とされます 。炎天下で活動する前に服用しておくと、水分代謝が整い熱中症を起こしにくくなるとも言われています 。
- 白虎加人参湯(ビャッコカニンジントウ): 強い熱と喉の渇きに用いられます 。この漢方薬には鉱物の石膏が使用され、体内にこもった熱を冷ます働きがあります 。炎暑で末梢血管が拡張し脳への血流が低下して起こる立ちくらみ(熱失神)にも効果的とされています 。予防目的でペットボトルなどに溶かして少しずつ飲用することも可能です 。ただし、清熱作用が強いため、胃腸の弱い人には冷え症状を悪化させる可能性もあります 。
- 生脈散(ショウミャクサン): 汗で失われた体液とエネルギーを同時に補う作用があるとされます 。暑気あたりでぐったりしたときの回復ドリンク的な漢方ともいえ、熱中症の初期〜中期予防、治療後の体力回復に広く用いられています 。
- 芍薬甘草湯(シャクヤクカンゾウトウ): 筋肉の痙攣・こむら返り(足がつる)や筋肉痛に効果を発揮します 。熱中症の典型症状である筋肉の硬直や痛み(熱痙攣)は発汗による電解質の乱れで生じますが、この漢方薬はそれを素早く緩和するとされます 。特に夜間、脱水が進んだ際に突然起こる足のつりなどに有用で、頓服薬として広く知られています 。
同じ症状でも体質や原因によって適切な漢方薬は異なるりますので、「あんしん漢方」での無料相談はいかがでしょうか。おすすめ漢方薬をご提案しますので、その結果をみてから購入するかどうかを決めることができます。
また、服用時の不安や悩みは、メールや相談フォームで、いつでも漢方医療チームに相談することができます。プライベートな内容でも、非対面なので、心置きなくご相談いただけます。 ご要望に応じて、LINEのビデオ通話を利用して診療を受けることが可能です。オンラインで受診できるので、病院や薬局へ出向く必要はありません。